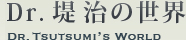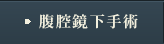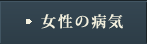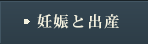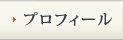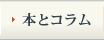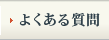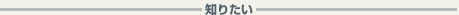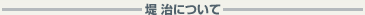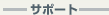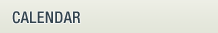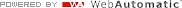東大医学部本館
[その他]

夢からさめて山王病院にもどり、これから午前の外来、午後は比較的難度の高い子宮内膜症の腹腔鏡下手術、夕方は会議と現実の世界に戻ります。
2008年05月13日 10:05 [その他]
天の時・地の利・人の和
[山王病院・国福大]
孟子は中国の戦国時代(紀元前)の儒学者です。昨日の母の日にちなむと、孟子の母親は教育に熱心で、孟母三遷という言葉もあるのはご存じでしょう。数々の名言が残されていますが、その一つに「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」があります。
山王病院では毎週朝礼がおこなわれ、私もお話をさせてもらう機会があります。今日の朝礼では、「天の時・地の利・人の和」を引合に新米院長の挨拶をいたしました。本来の孟子の言葉からはすこしずれますが、よい医療が求められているのは天の時かもしれません。港区赤坂は地の利があるともいえます。それより大事なのは、患者さん本位の山王病院の理念のもとに職員全員が心を一つに努力することといえましょう。山王病院がよりよい医療を提供できるよう私もがんばります。
山王病院では毎週朝礼がおこなわれ、私もお話をさせてもらう機会があります。今日の朝礼では、「天の時・地の利・人の和」を引合に新米院長の挨拶をいたしました。本来の孟子の言葉からはすこしずれますが、よい医療が求められているのは天の時かもしれません。港区赤坂は地の利があるともいえます。それより大事なのは、患者さん本位の山王病院の理念のもとに職員全員が心を一つに努力することといえましょう。山王病院がよりよい医療を提供できるよう私もがんばります。
2008年05月12日 19:02 [山王病院・国福大]
母の日
[プライベート]
今日は母の日皆さんはお母さんにカーネーションを送りましたか。
母や女性に感謝し祝う風習は昔からあったようですが、「母の日」を5月の第2土曜に定めたのは、1914年アメリカ議会で、カーネーションを含めアンナさんという女性の呼びかけがもとであったと聞きます。
私はといえば、実家の両親が上京し、山王病院の近くで昼食を一緒に食べました。午前の外来が予定より長引いたので遅刻してしまいましたが、久しぶりに家族団欒を楽しめました。両親が健在でいてくれることは本当にありがたいことです。
余談ですが、私の祖父は1900年生まれ、私は1950年、孫は2000年を少し過ぎて生まれましたがおよそ25年を一世代と考えることができます。子どもの頃算数好きな私は、祖父を起点に子どもを二人もつとして計算してみました。子孫は2000年には16人でこれはクリアしています。2100年は256人、2200年には4096人。これ位はいいとして、2400年はおよそ100万人、2600年には2億5600万人になりました。もちろん、そんなはずはなく、閑話休題でこれ以上の説明は省き、仕事に戻ります。
母や女性に感謝し祝う風習は昔からあったようですが、「母の日」を5月の第2土曜に定めたのは、1914年アメリカ議会で、カーネーションを含めアンナさんという女性の呼びかけがもとであったと聞きます。
私はといえば、実家の両親が上京し、山王病院の近くで昼食を一緒に食べました。午前の外来が予定より長引いたので遅刻してしまいましたが、久しぶりに家族団欒を楽しめました。両親が健在でいてくれることは本当にありがたいことです。
余談ですが、私の祖父は1900年生まれ、私は1950年、孫は2000年を少し過ぎて生まれましたがおよそ25年を一世代と考えることができます。子どもの頃算数好きな私は、祖父を起点に子どもを二人もつとして計算してみました。子孫は2000年には16人でこれはクリアしています。2100年は256人、2200年には4096人。これ位はいいとして、2400年はおよそ100万人、2600年には2億5600万人になりました。もちろん、そんなはずはなく、閑話休題でこれ以上の説明は省き、仕事に戻ります。
2008年05月11日 19:01 [プライベート]
医療ルネサンス
[医療・医学など]
「医療ルネサンス」は1992年から読売新聞が患者さんに役立つ医療最新情報を分かりやすく提供しているもので、私も愛読しております。10年以上前ですが、子宮内膜症の腹腔鏡下手術も取り上げて頂いたことがあり、東大ばかりか日本の腹腔鏡下手術の普及・拡大のきっかけの一つになったと記憶しています。
今回、不妊治療をとりあげられ、生殖医療に携わる者として、特に注目して拝見しました。不妊治療の現場に密着、掘り下げた良い企画だと思いましたが、少し気になる事がありましたので、ここで皆様にも考えて頂きたいと思います。
不妊症の原因は、大きくわけて排卵因子・卵管因子・男性因子の三つであることはご存知でしょう。その原因を究明して治療をおこない、できるかぎり自然な形で妊娠が成立することが望ましいのは言うまでもないでしょう。
上に述べた三因子の検査を進めて、卵管に問題があるとされた場合や子宮内膜症が疑われた場合、あるいは原因がはっきりしない場合には腹腔鏡による検査・手術を適用するのは教科書的というか王道であると思います。
今回の「医療ルネサンス」では、限られた紙面のためでもあるでしょうが、これらの医学的なステップへの言及があまりされず、体外受精や顕微授精さらに新しいテクノロジーが紹介され、不妊=体外受精という誤解を生ずることが危惧されます。
今日の記事でも子宮内膜症の患者さんが体外受精で治療されていまいたが、その前に腹腔鏡下手術を受けられたのか気になるところでした。
もちろん、ケースによっては、これらのステップをとばして、一気に体外受精や顕微授精に進む選択肢もあってよいと思われますが、その場合も十分なインフォームドコンセントが必要でしょう。日本産科婦人科内視鏡学会理事長として不妊症の診療ガイドラインを作っている立場もあり、不妊症の特集最終日にあたり、ひとこと発言させて頂きました。
今回、不妊治療をとりあげられ、生殖医療に携わる者として、特に注目して拝見しました。不妊治療の現場に密着、掘り下げた良い企画だと思いましたが、少し気になる事がありましたので、ここで皆様にも考えて頂きたいと思います。
不妊症の原因は、大きくわけて排卵因子・卵管因子・男性因子の三つであることはご存知でしょう。その原因を究明して治療をおこない、できるかぎり自然な形で妊娠が成立することが望ましいのは言うまでもないでしょう。
上に述べた三因子の検査を進めて、卵管に問題があるとされた場合や子宮内膜症が疑われた場合、あるいは原因がはっきりしない場合には腹腔鏡による検査・手術を適用するのは教科書的というか王道であると思います。
今回の「医療ルネサンス」では、限られた紙面のためでもあるでしょうが、これらの医学的なステップへの言及があまりされず、体外受精や顕微授精さらに新しいテクノロジーが紹介され、不妊=体外受精という誤解を生ずることが危惧されます。
今日の記事でも子宮内膜症の患者さんが体外受精で治療されていまいたが、その前に腹腔鏡下手術を受けられたのか気になるところでした。
もちろん、ケースによっては、これらのステップをとばして、一気に体外受精や顕微授精に進む選択肢もあってよいと思われますが、その場合も十分なインフォームドコンセントが必要でしょう。日本産科婦人科内視鏡学会理事長として不妊症の診療ガイドラインを作っている立場もあり、不妊症の特集最終日にあたり、ひとこと発言させて頂きました。
2008年05月09日 23:34 [医療・医学など]