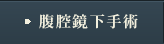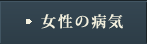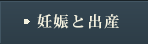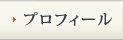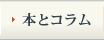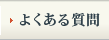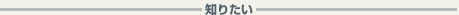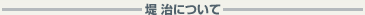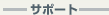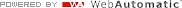女性の病気 | 子宮の病気について
子宮筋腫の手術:子宮全摘術
子宮筋腫は婦人科で扱う疾患の中で最も頻度の高いもののひとつですが、手術療法としては子宮全摘術による根治手術と筋腫核出による保存手術があります。この両方に腹腔鏡または子宮鏡といった内視鏡下手術が適用されます。本日は主として腹腔鏡を利用した子宮全摘手術について、その適応、術式の実際、利点や 問題点についてお話したいと思います。
子宮全摘術のアプローチとしては従来より開腹しておこなう腹式と腟式がありました。腟式は開腹を回避でき患者さんに対する侵襲は少ない優れた術式で、現在でも、もちろん行われています。ただし腟式では視野も限られ、安全な実施にはいくつかの制約があり、適応は限られています。すなわち腟式を選択する場合は、第1に、開腹の既往がなく腹腔内癒着がないこと、第2に経産婦で腟式操作が容易であること、第3に子宮の大きさに限度があり、手拳大以下である等を必要条件とされています。そのため腟式例は数も限られ腹式手術が大半を占めてきました。
しかし癒着が強度の子宮筋腫や子宮内膜症患者でもあるいは子宮の大きさが手拳大以上の場合でも腹腔鏡の応用で開腹を回避した子宮全摘術が可能になってきました。そこで子宮全摘術のアプローチは腟式が容易に可能な例においては腟式を実施し、従来開腹を必要としていた症例に腹腔鏡下手術を選択するということになります。つまり、開腹の既往があり腹腔内癒着が予想される場合や、未産婦で腟式操作が困難な場合、子宮の大きさが手拳大以上の場合等に腹腔鏡下手術が選択されます。
ただし腹腔鏡下手術もすべてに万能ではなく、成人頭大を越えるような大きな筋腫の場合は視野も悪くなり、相対的に手術の実施が難しくなります。そのような巨大筋腫にはGnRHによる偽閉経療法で低エストロゲン状態にし、子宮を小さくしてから実施するなどの工夫も必要となります。
腹腔鏡を利用した子宮全摘術においても子宮は腟より回収します。腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術は、腹腔鏡下手術と腟式手術の併用の割合により laparoscopically-assisted
vaginal hysterectomy(LAVH)、laparoscopic hysterectomy(LH)、total laparoscopic hysterectomy(TLH)に分類することができます。どの術式を選択するかは症例の子宮可動性(経産か未産か)、腹腔内の癒着の程度、子宮の大きさなどによります。
laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy(LAVH)は腹腔鏡下腟式子宮全摘術とも呼ばれますが、子宮附属器や円靭帯の処理を腹腔鏡下手術でおこない、しかる後に腟式に子宮全摘をおこなうもので比較的よく行われます。
laparoscopic hysterectomy(LH)は腹腔鏡下子宮全摘術と呼ぶこともありますが、附属器・円靭帯に加え子宮動脈基靭帯までも腹腔鏡下に処理し、腟壁切断は腟式におこなうものです。子宮内膜症合併による癒着例等で実施されます。
未婚女性等で腟式操作が困難な場合には腟断端の縫合も含め腹腔鏡下にすべての操作をおこなうtotal laparoscopic hysterectomy(TLH)全腹腔鏡下子宮全摘術がおこなわれます。これは腹腔鏡下手術への依存度が高く、術者が縫合操作を含め腹腔鏡下操作に熟練していることが前提とします。
手術の手順としては、まず腹腔鏡を挿入し腹腔鏡内を観察し、腹腔鏡下手術の可否および上記術式のいづれを選択するかを決定し手術操作にうつります。腹腔内に癒着のある時はレーザー、超音波メス、または電気メスなどで剥離操作をおこないます。次いで円靭帯および付属器の切断をおこないます。これら靱帯の切断にはエンドカッター、エンドGIAといった自動縫合器の利用が便利ですが、バイポーラー電気メスで凝固した上で、はさみ鉗子で切断するのが経済性などを 考えても有利です。
LAVHの場合はこれら靱帯を切断したところで腟式操作に移り、腟管の切断・子宮動脈の処理は腟式に実施します。LHの場合子宮動脈・基靭帯の処理を腹腔鏡下に実施し、その後腟式に腟管の切断をおこなう。TLHの場合はさらに腹腔鏡下に腟管の切断も実施する。
腹腔鏡下子宮全摘術の利点は、創が微小(5-10mm)で開腹を回避できることによるということができます。術後疼痛が微小で鎮痛剤不要例が大半であり、入院期間も術後5-7日で退院と開腹術に比べ短縮される。当然のことながら早期社会復帰可能であり、個人にとっても社会にとっても大きな利点となる。
また腹腔鏡下手術の特徴すなわちスコープの適切な使用により骨盤内の死角は解消され、しかも拡大した術野で手術をおこない、より安全で容易な術式となりうる。ただし、特殊機器・器具を必要としたり、全身麻酔で骨盤高位の体位を必要とするなどの制約の他に気腹等による腹腔鏡下手術に特異的な合併症がありうることも欠点として理解しなければならない。小児頭大以上の大きな子宮筋腫では摘出物回収に難があることも事実である。
腹腔鏡下子宮全摘術は患者に対する侵襲を軽減することが期待される。先に述べた各々の術式による成績を出血量を指標に比較すると興味深い結果が得られました。腟式に腟管の切断・子宮動脈の処理をおこなうLAVHの場合より子宮動脈・基靭帯の処理を腹腔鏡下に実施するLHで有意に出血量は少なく。腹腔鏡下に腟管の切断も実施するTLHではさらに少量であった。LHやTLHを選択するのは子宮内膜症合併例や未産婦で腟式操作が困難な例であり、出血量は多くな ることが予想されたがまったく逆の結果が得られた。これは腹腔鏡下に操作することによる利点が活かされた成果と考えられる。開腹術をおこなった子宮内膜症
合併例との比較はLHやTLHが単に開腹を回避するのみでなく、術式として優れていることを示している。
腹腔鏡下子宮全摘術の合併症
腹腔鏡下子宮全摘術の合併症としては子宮全摘術の合併症と腹腔鏡下手術に特異的ものとがある。子宮全摘に特異的なものについて予防対策や術中の工夫を含めて個々に述べる。
膀胱損傷
膀胱は子宮頚部前面を覆っており子宮全摘術においては子宮より剥離する。従って剥離操作時に損傷の危険がある。注意としては開腹手術でも同様であるが、留置カテーテルをおき膀胱内は空虚にした上で膀胱剥離をおこなう。術中は尿量と血尿の有無等の尿の性状をチェックする。膀胱損傷が疑われたときは色素(インジゴカルミン)を留置カテーテルから膀胱内に充満させ、流出の有無を観察する。直腸・腸管損傷
直腸は子宮後面との間にダグラス窩を形成しており通常の子宮全摘術においては損傷の危険は少ない。しかし子宮内膜症等で直腸ないし腸管が子宮に癒着しダグラス窩が閉塞しているときは子宮より剥離する必要がある。この場合癒着の程度は強いことが多く剥離操作は慎重におこなっても損傷の危険が高い。従って、直腸の癒着が予想される症例においては術前に抗生剤および腸管洗浄剤を投与する。実施の際は局所にスコープを接近させ拡大した視野で操作し、腟側より綿棒等を挿入ダグラスを確認したり、直腸診を施し直腸損傷のリスクを極力少なくする。尿管損傷
尿管は子宮動脈下方を交差するように走行して膀胱に進入する。通常のLAVHでは子宮動脈の処理は腟式であり腹腔鏡下手術で損傷することはない。しかし附属器と尿管の走行する広靭帯が癒着している場合やLHないしTLHをおこなう場合は子宮動脈を腹腔鏡下に処理切断する必要があり尿管損傷の危険も生ずる。尿管損傷を未然に防ぐには腹腔鏡で尿管の走行を確認するかあるいは広靭帯を開放して尿管を剥離し癒着臓器や子宮動脈より遊離せしめることが必要になる。尿管損傷の修復はダブルJカテーテル留置等の保存的方法が採られることもあるが手術的処置が必要なこともある。先に述べたように腹腔鏡下子宮全摘術は開腹を回避して、患者に対する侵襲を軽減するのみならず、入院期間の短縮(医療費の抑制)や早期社会復帰など社会全体にとっても大きな利点となる。しかしながら、特殊機器・器具を必要とする点はさておいても、腹腔鏡下子宮全摘術特にLHやTLHの術式の修得には熟練を要し、そのためのトレーニングは本手術手技が安全に普及するためには最も重要な課題である。
腹腔鏡下手術を予定してスコープを挿入しても腹腔内の癒着や卵巣腫大等が合併し術野不良の場合で子宮が観察できないときは腹腔鏡下手術を断念し開腹手術に移行する。オリエンテーションの不良な状態下の腹腔鏡下手術は困難を伴い、手術時間を含めた患者への侵襲という点で開腹にまさるとは言いがたい。この選択を誤った場合、臓器損傷等の合併症のリスクは高まり、開腹を余儀なくされる可能性も高まる。また術中注意すべき合併症で述べたように臓器損傷の修復や大出血への対応の場合開腹に移行することにより患者への侵襲をより少なくする場合もある。術者はその点を銘記し、患者にもいわゆるインフォームドコンセントのもとで手術を実施する必要がある。
本日は子宮筋腫の腹腔鏡下手術として子宮全摘術をお話しましたが、子宮がん手術への応用もこれからの問題です。上皮内がんの治療では腹腔鏡下手術をおこなうことには疑問の余地は少ないと思います。ある程度進行した癌の手術いわゆる広範性子宮全摘術を腹腔鏡下手術でおこなうことは、欧米では報告があります。日本においても当然議論の対象となることが予想されますが、今後の問題といえましょう。