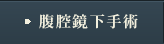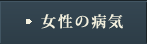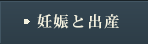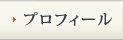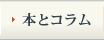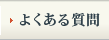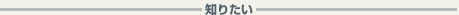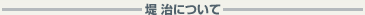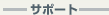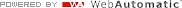腹腔鏡下手術 | 腹腔鏡下手術論
子宮疾患の腹腔鏡下手術
子宮筋腫に対して従来開腹術式で根治手術すなわち子宮全摘術あるいは保存手術すなわち筋腫核出術が実施された。腹腔鏡下手術の適応により、子宮全摘術はもちろん筋腫核出術も腹腔鏡下におこなわれるようになった。また粘膜下筋腫に対しては子宮鏡下手術も広く実施される。
子宮全摘術
子宮全摘術の方法としては開腹しておこなう腹式と腟式があった。腟式は開腹を回避でき患者に対する侵襲は少ないが、安全な実施にはいくつかの制約があった。すなわち腟式を選択する場合は、1)開腹の既往がなく腹腔内癒着がない、2)経産婦で腟式操作が容易である、3)子宮の大きさが手拳大以下である等を必要条件としていた。しかし腹腔鏡の応用で癒着が強度の子宮内膜症患者や子宮の大きさが手拳大以上の場合でも腹腔鏡を利用した子宮全摘術が可能になった(図3)。
図3.骨盤内の解剖
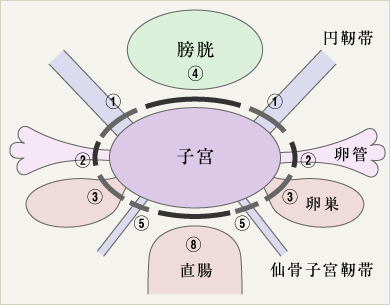
手術の選択をおこなう際に注意しなくてはならないのは、腟式が容易に可能な例においては腟式を実施するのが当然で腹腔鏡下手術を選択すべきではないということである。従って先に述べた腟式選択の条件を満たさないもの、例えば開腹の既往があり腹腔内癒着が予想される場合、未産婦で腟式操作が困難な場合、子宮の大きさが手拳大以上の場合等である(図4)。ただし腹腔鏡下手術も万能ではなく、特別な場合には開腹手術を選択する。例としては、腹腔内癒着が極めて強固で腹腔鏡で子宮の確認が不可能な場合、子宮底が臍上をはるかにこえる極めて巨大な場合等が挙げられる。この選択を誤った場合、臓器損傷等の合併症のリスクは高まり、開腹を余儀なくされる可能性も高まる。
図4.子宮筋腫の手術療法
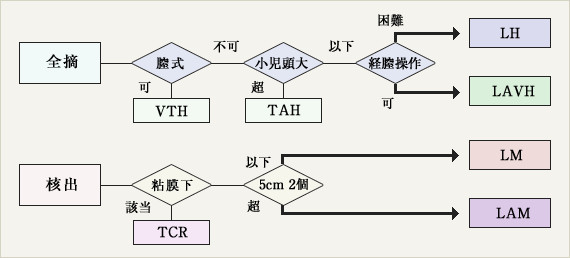
腹腔鏡を利用した子宮全摘術は腟式手術の併用の有無あるいは併用の程度により大きく3つに分類される。どの術式を選択するかは症例の子宮可動性(経産か未産か)、腹腔内の癒着の程度、子宮の大きさなどによる。通常の子宮筋腫等に対する子宮全摘術としては腹腔鏡下に癒着剥離をおこない附属器・円靭帯の処理程度をおこないしかる後に腟式に子宮全摘をおこなうLAVH(腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術)が適用される。子宮内膜症合併による癒着例等では附属器・円靭帯に加え子宮動脈基靭帯までも腹腔鏡下に処理し腟壁切断は腟式におこなうLH(腹腔鏡下子宮全摘術)が適する。未婚女性等で腟式操作が困難な場合には腟断端の縫合も含め腹腔鏡下にすべての操作をおこなうTLH(全腹腔鏡下子宮全摘術)もおこなわれる。
筋腫核出術
腹腔鏡下子宮筋腫核出術の適応は過多月経、月経困難症などの症状がある場合で開腹での子宮筋腫核出術の適応と同じである。筋腫が存在するだけでは手術適応とはならない。また手術の難度を考慮して筋腫核が2個以内かつ最大筋腫核の直径5cm以下のものであることを腹腔鏡下手術の要約としている(東大)。多発性の筋腫や直径5cm以上の筋腫であっても技術的には充分腹腔鏡下に核出可能であるが、手術時間の著しい延長が予想される場合は患者への侵襲の面でむしろ開腹手術を選択すべきである。
腹腔鏡下子宮筋腫核出術や子宮内膜症性嚢胞(チョコレート嚢腫)核出術などの術前にはGnRH agonistによる術前薬物療法が勧められる。子宮筋腫の場合腫瘍径の縮小、筋腫核への血流の減少、筋腫核の正常筋層からの剥離操作の容易化等の効果があげられる。腹腔内の制限された空間の中では腫瘍の縮小は視野および操作性を向上させることは言うまでもない。投与期間は薬剤により異なるが、通常2-6カ月間おこなう。